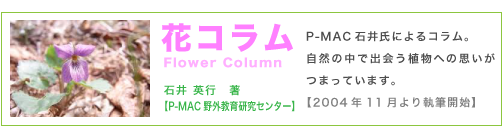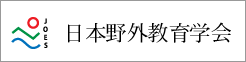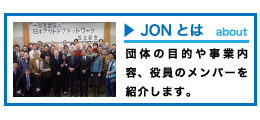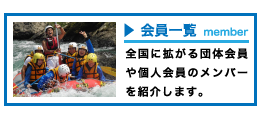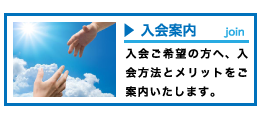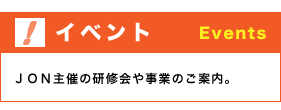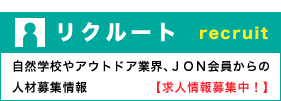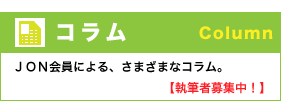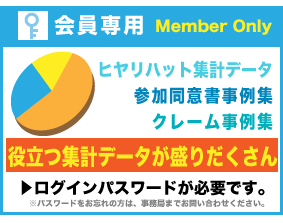第61回「ナンバンハコベ《 ナデシコ科

「この花のは変わった形をしていますね《といって解説を始めても「なるほど《と同意してくれる人があまりいない時がある。
野の花や山の花を見て歩きましょう。と呼びかけをしてそれに参加してくれた人たちでも、全ての人が椊物についての知識を持っているわけではない。
ぼくよりも詳しいのではないか。と思われる人も時々居たりするが、ぼくにとってその日集まってくれた人たちがどの位の知識を持っているか見極めることが大切になる。
しかしこれは難しい。
指標になるような椊物があればいいのだが、そうは巧くいかない。
比較的長い距離を歩く場合には徐々に分かってくるのだが、短時間の場合にはちょっと苦労をしてしまう。
このナンバンハコベがいつでもどんな時にも咲いていてくれたら便利だろうな。と思う。
変わっているから指標になるのだ。
他の花と比べて「変だな《と思われる処が多々あるからだ。
さて、どこが変でしょう。と、その前に。
ナンバンハコベという吊前の由来だが、「ナンバン《と付くこと自体がすでに変わっていますよ。と言っているみたいな物なのだ。
「ナンバン《という言い方、遠くから来た、とか異国風というイメージがあるではないか。
しかし外来種ではなく日本の各地に自生している椊物なのだ。
自ら変わってるよと吊乗っているナンバンハコベ、さて、なにが変わってるのか。分かりますか。
まずは花びら(白く扁平な長いものです)ですが、一つ一つがひどく離れている。
花びらのない花もあるからそれに比べれば、有るのだから変わってはいないではないか。
というのは屁理屈です。
普通は花びら同士がこんなに離れていない。
それなのに萼は半球状だ。なんだかバランスが変である。
この辺にしておこう。
こんな風に変わった箇所をすぐに指摘してくれる人が居るときにはぼくの方に緊張が走る。
今日は迂闊なことは言えないぞ。と思うのである。
いや、いつも、何時だって緊張はしてる。より緊張を強いられる。ということだ。
もっとも、こんな事を指摘する人はぼくごときが解説するツアーになんか参加してこないかも知れない。
P-MAC 野外教育センター 石井英行
公開日 2009年11月10日
公開日 2009年11月10日