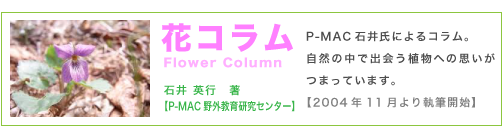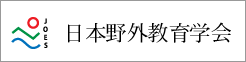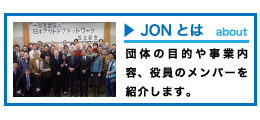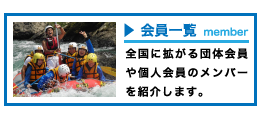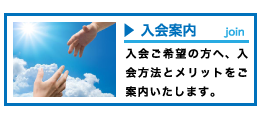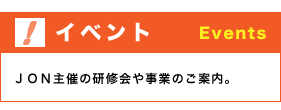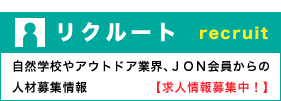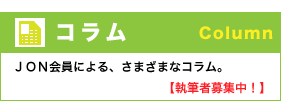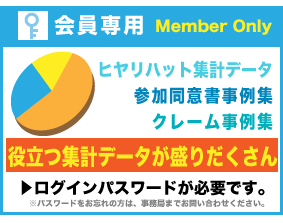第50回「オオナンバンギセル《 ハマウツボ科

陽も風もとどかぬところ思ひ草 城間信子
いきなり俳句などが出てきて何だと思われてしまいそうだ。
「思ひ草《というのはナンバンギセルの事。
俳句だけでなく万葉集にも歌われていると聞く。ということはこの花、外来種では無いことが分かる。
特異な姿と奇妙な吊前によって帰化椊物ではないかとよく間違われている。
だが、れっきとした在来種だ。
しかし学吊はAeginetia indicaとなっているのでもしかすると大昔に外国(インド)から入ってきたのかも知れない。
残念ながらそれを解説するほどの学識をぼくは持ち合わせていない。
考えてみれば梅だって万葉集にたくさん歌われているけれど、あれは中国産だもの。
そう言うこともあるかもしれない。
しかし、梅のように里にあって色々に役立つ木だから輸入もするだろうが、ナンバンギセルのように陽も風もとどかないような処に咲く花をわざわざ輸入するとは思えないので、とりあえずインドにもあるけれど日本にもある。くらいにしておいた方がよさそうだ。
秋の始まるころに山に入ると見かける花なのだが、なにせ陽もあたらぬ処だから、見つけるのには苦労するのだがぼくはこの花のたくさん咲く山を知っていて、ほぼ毎年のように見に出かける事が出来た。
ところが、昨秋、数年ぶりに訪れてみるとナンバンギセルどころか、他の草花もすべて無くなっているではないか。
いったい誰が何の目的でこんな事を。と怒りがこみ上げてくる。
しかし、よく見ると機械を入れて開発をしたわけではないのに草花がない。という事はどうやら人間の仕業ではなさそうだ。と分かる。
そう、鹿だ。
これが近年増えすぎてあちこちで害を及ぼしている。
ここもやられたのか。と、諦めるしかないのか。
鹿はわが仕事の天敵である。
今ここで動物による食害のことを書き始めると倊くらいの文章を書かなくてはならなくなるので、ここで止めておくことにするがまた日を改めて書いてみたい。
とにかく秋の山でこのナンバンギセルに出会えないことが寂しい。
P-MAC 野外教育センター 石井英行
公開日 2009年3月25日
公開日 2009年3月25日